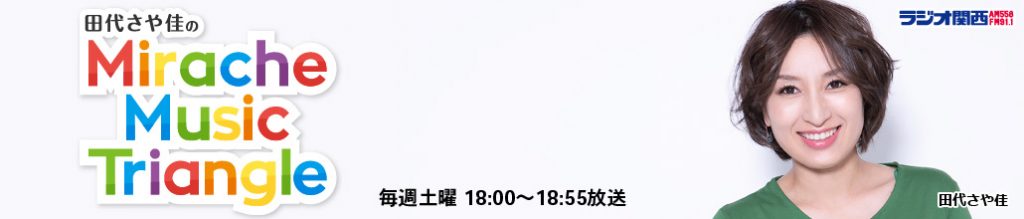シンガーソングライター、ギタリスト、プロデューサーとしても活躍する伊藤銀次が、ゲスト出演した音楽トーク番組『田代さや佳のMirache Music Triangle』(ラジオ関西、土曜午後6時~)の単独インタビューで思いを語った。2回にわたる放送の後編となった1月11日の回では、「音楽とプロデュース」をテーマに話を進めた。
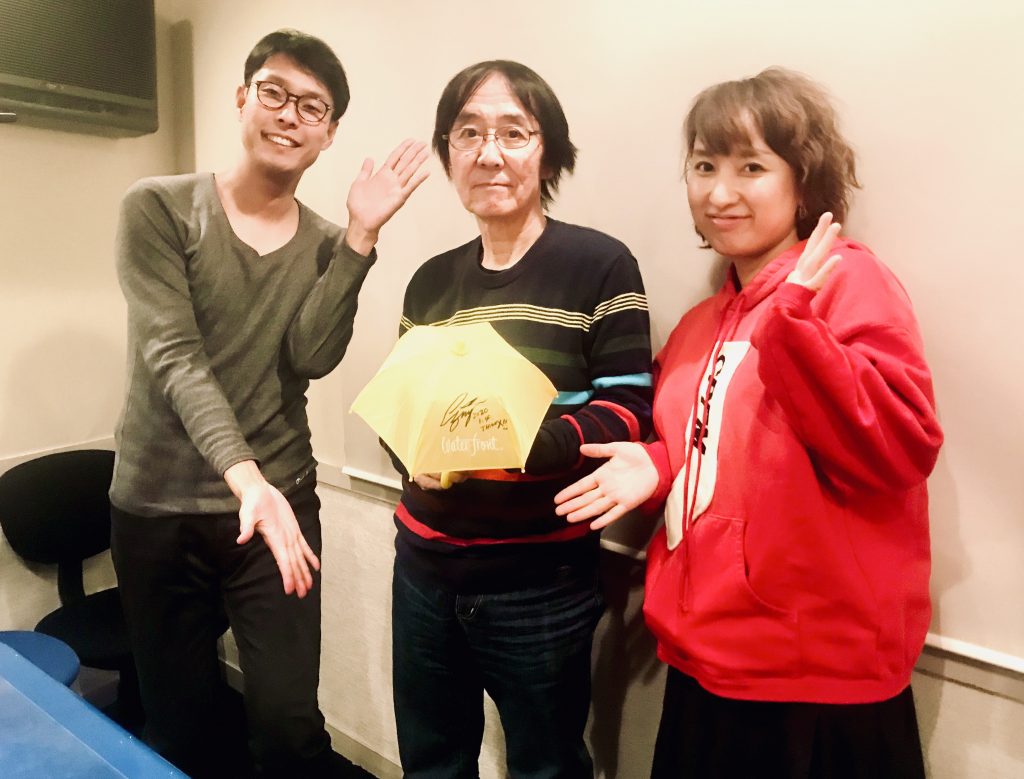
ビートルズが教えてくれた。それが僕にとっての『プロデュース』の始まり
日常の中でのこだわりについて、音楽を聴くと「どうしても、そっちのモードになるので」、なるべく音楽以外で自分がリラックスをすることを考え「ジョギング」をしているという、伊藤。大会を目指してというより、ゆっくりとできるだけ長い時間、遠くまで走るスタイルを続けている。「血行が良くなって、頭がスッキリして、逆にフラットな気持ちで」仕事に取り組め、走っているときに、メロディーが浮かんでくるそうだ。
「いつもiPhoneを持ち歩いているので、隅っこに行って(音を吹き込む)。あんまり大きい声で歌えないだけど(笑)。曲ってのは、いつ出てくるか分からないんですよ! 蝶が森の中からバーって出てくるようなもので、そのときに捕まえないと、その曲はもう二度と出てこないんです」と、伊藤は今でもあふれるアイデアをメモしていると語る。
また、「子どもの頃から音楽好きだし、一度聞いたメロディーは、忘れないっていうのもあるんでしょうね。でも、それは誰でもできることだと思っていました、子どもの頃は」という幼少期のエピソードから、今だから思う音楽感性を磨いた時期の話に入っていく。
伊藤が子どもの頃、まだ今のように音楽出版社からコピー本(曲をコピーするための譜面)などもない時代は、ビートルズなどをカバーしようと思ったら自分で耳コピするしかなかった。初めは(音楽の)知識もなく、コード本を買ってきて「コピーしたいレコードの曲の頭に針を下ろすんですよ! 『ジャ!!』って音が響きますよね。そこで『ジャ』の音をギターで探すんです。これをずっとやって、最初の曲は(コピーに)1か月くらいかかりましたよ」。
これをきっかけに「(音楽)世界に入れるんだよね、耳がよくなってくるので。それでノートにコードが埋まってくるんですよ。そしたらもっと難しい曲をやってみようとなって。こんなことができる人が(当時周りに)いなくて、バンドを4つくらい掛け持ちしていましたよ」と、自身の音楽家の始まりを語る。
「やっぱりビートルズが教えてくれた。それが僕にとっての『プロデュース』の始まり。歌を歌いたいけど、歌を歌うためにギターを弾いて伴奏も必要でしょ!? 伴奏してもビートルズみたいに、ドラムやギターがいなきゃいけない。バンドになってなきゃいけない。友達に聞かせて教えて、バンドを作るところから始めなきゃいけないのだから」
そうやって、歌うためにバンドを作って、友達に音楽を教えてバンドを仕切ることの繰り返しが、プロデューサーとしての感覚を身に付けた契機だろうと伊藤は語る。
「沢田研二さんとか『(曲を)アレンジしてください』と来たときも、ボーカルが沢田研二さんのバンドを仕切っていた、だけなんですよ。そういう発想なんです」。自分がやりたい音楽をプロデュースまで誰もやってくれる訳ではない。だから自分がやっているだけ、なんだと言う。
ウルフルズはとんでもない切り口から行くバンドなんだという予感があった
伊藤がプロデューサーとしてのキャリアのスタートしたのは、1977年。大阪のロックバンドの登竜門と呼ばれていたコンテスト「8.8ロックデイ」で優勝したブルース・バンドの花伸(ハナシン)を担当したところからだ。憂歌団のベーシスト花岡献治の弟、花岡伸二が率いる、当時としては珍しい日本語で歌うブルース・バンドだった。
「どうやっていいか分からなかったから、大瀧(詠一)さんにプロデュースしてもらったのを参考に、体当たりでやりました。結果的に売れなかったんだけど……」。その花伸でギタリストだったのが、当時高校生で、その後、90年代にZARDや、T-BOLAN、WANDS、大黒摩季、DEENなどのアレンジャーとして大ヒットを送り出す、「銀次道場の門下生」葉山たけしだった。
その後、伊藤のプロデュースで欠かせない存在となるのが、ウルフルズだ。
ウルフルズは、1996年の「ガッツだぜ!!」や「バンザイ〜好きでよかった〜」で世に鮮烈な印象を与えると、アルバム「バンザイ」は、100万枚を超える売り上げを記録。これを機にウルフルズは音楽業界の第一線で活躍し続けるバンドとなる。そこにプロデューサーとしてクレジットされていたのが、伊藤だった。
その当時、アレンジだけでなく、曲や詞を書く段階から関わらせて欲しいと考えていた伊藤に舞い込んだ、ウルフルズのプロデュース。そのやり方は、正にマンツーマン。スタジオに入るとき、一緒に入って、好きなフレーズや好きな音楽の話を聞きながら進めて行った。「スタジオ・ミュージシャンではないから、彼らのなかにないものはできないから」。そんな思いで、コミュニケーションを取りながら、彼らの潜在能力を引き出す方法を試行錯誤する。スタッフも含めて、1年ぐらい練り上げて生まれたのが「ガッツだぜ!!」だ。
「後付けになるかも」と注訳しながらも、Mr.Childrenやスピッツみたいな王道ではなく、RCサクセションや、サザンオールスターズの『勝手にシンドバット』のように、ウルフルズはとんでもない切り口から行くバンドなんだという予感が、伊藤にはあった。
「僕はね。トータス(松本)君に会うたびに、『勝手にシンドバッド』みたいな曲を作ってよって言っていたんだよ。彼は何のことが分からなくて、『は〜い〜』って(生返事)言ってたけどね」
トータス松本は、ミスチルやスピッツみたいなヒットするメロディーも書ける才能があり、どちらかと言うと、卒なくいい曲が書ける人だったと感じていた、伊藤。「トータス君の歌い方にあった曲、破裂するリズムみたいな曲が欲しかったんだよ」。それを『勝手にシンドバット』のような曲だと表現していた。そして、できたのが「ガッツだぜ!!」だった。
ウルフルズ、プロデュースのテーマは、「ロックバンドが魂を売って、ディスコをやる」
元々は、(トータスが)冗談で作った曲の中に「ガッツだぜ!」というフレーズがあり、曲そのものはなかったが、伊藤は「ガッツだぜ!!」というフレーズに大きな可能性を感じたという。
「スタジオに入って、リズムパターンから一緒に作った。『ディスコをやろう』って」。伊藤がそう提案すると、ウルフルズのメンバーは驚いたという。それでも、「テーマは、ロックバンドが魂を売って、ディスコをやる」こと。ここにも伊藤の”確信“があった。「ウルフルズに初めて会ったとき、トータス君がね、『僕たちバッタもんバンドです』って言うんだよ。『バッタもんのブルース、なんちゃってサーフィンなんですよ! でも、僕らはこれが好きなんですよ』と。面白いことを言うやつらだと思って。それで、『なんちゃってディスコだよ』となった」
そこから、リズムパターンを決め、トータスにはメロディーを作ってもらい、みんなでアイデアを出しあって1日でできたのが、ウルフルズ最初のスマッシュヒットにつながる。
ちなみに、「バンザイ」ができたときは、「表を歩いてるときに浮かんじゃった。『バンザ〜イ、キミに 会えてよかった』って」とのこと。「携帯とかない時代だから、あわてて電話ボックスに入って、自分の家に電話をかけて留守テル(留守番電話)に入れたんだって! 本当に、ところ構わず(メロディーが)出てくるんですよ。メロディーが出てくるときは、後ろにドラムも鳴ってるんですよ。実際に鳴っているというより、イメージがされているんですよ」と音楽家ならではのエピソードも話していた。
「同じように、同じ時期に、多くのバンドをプロデュースしたけど、返って来たのは少なくて……。やっぱり彼らは、何かを持っていたんだね」と伊藤は当時のウルフルズについて語った。
1950年生まれ、今年で70歳を迎える伊藤。ミュージシャンとしても精力的にライブも続ける彼にとって、ライブで一番好きな瞬間を聞くと、言葉を詰まらせつつ、少し照れ臭そうに述べる。
「照れ臭いんだけど(歌の音程が)高いところで、ピーンと(自分の声が)響いたとき。長年やっているけど、いつもレコーディングと同じクオリティーで歌いたいと思ってる」。
はにかむ笑顔に、まだまだ続くミュージシャン伊藤銀次の活躍がますます楽しみになった。
伊藤銀次 New Album「RAINBOW CHASER」
(2019年12月4日リリース)