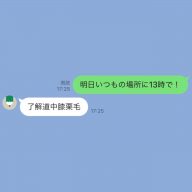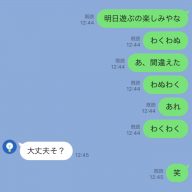「あんじょう」。東海道新幹線の駅「三河安城」のことではありません。関西弁の「あんじょう」です。「あんじょうやりや」などと使います。アクセントは、「じょ」が高い“中高(なかだか)型”です。

『都道府県別全国方言辞典』(三省堂)には、「あんじょー」との表記で「大阪府」の項目にありました。この言葉は、関西ではある程度年齢の高い人を中心に使われていて、残念ながら、若い年代では知らない人が増えています。
会話の中では「あんじょうやりや」などと使い、その場合は「うまいことやってな」「丁寧にやってな」などの意味合いで用いられます。では、「あんじょう」という言葉そのものが持つ意味は?
『新明解国語辞典 第八版』(三省堂)によりますと、「『細かいことはとやかく言わないで、結果としてうまくいく』の意の関西方言」とあります。ところが、その前に「『味良く』の変化」とありました。
篠崎晃一さんの著書『それいけ!方言探偵団』(平凡社新書)にくわしく書かれていますので、少し紹介します。
「由来は味覚を表す『味良し』が、『あじよく→あじよう→あんじょー』として変化して生まれ、江戸時代の滑稽本(こっけいぼん)でも使われる。『塩梅(あんばい)、うまい』などと同様、味の表現から行為や物事の進展の巧みさを表すように意味が広がったとされる」(一部抜粋)
そういえば、私が幼い頃、調理の場で「そこ、あんじょうな」などと言いながら、年配の女性が若い人にアドバイスをしている様子を見たことがあります。元々そこからきた言葉だったのですね。
普段の会話で表現が変化していくことは、現代でもよくあります。いま、当たり前のように使っている言葉も、将来大きく変わっていく可能性はあります。でもそれこそが、「言葉が生きている」証しだと言えます。使われる限り、言葉は生き続けます。そういう意味からすると、これらは「変化」ではなく「進化」と捉えられそうですね。
言葉は時代とともに、その意味も使い方も変化します。「ことばコトバ」では、こうした言葉の楽しさを紹介していきます。