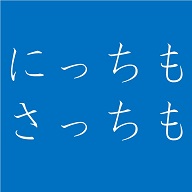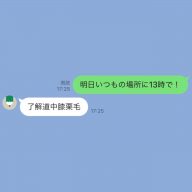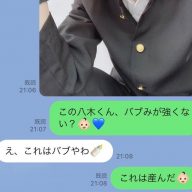語源も調べました。『日本語源大辞典』(小学館)によると……
「『すばらしい』の『す』に『てき(的)』のついたもの。『素敵』はあて字」とあり、意味は「(1)程度がはなはだしいさま。度はずれたさま。滅法。(2)非常にすぐれているさま。すばらしい」とありました。そして語源説には「《一部略》(1)が本来の意味で、19世紀初頭ころから、江戸のやや俗な流行語として、庶民の間で用いられたものらしい。」さらに「明治に入ると(2)の意味に限定されてくる。《以下略》」と記載。
明治時代までは「素敵」は「はなはだしい」「滅法」などの意味で使われていたんですね。
『桜姫東文章』のセリフ、酒は「素敵に飲んだ」というのは、「酒を滅法(たくさん)、たらふく飲んだ」という意味だったんですね。なるほど……納得!
さらに語源大辞典には、「すてき」の漢字表記について次のように載っていました。
「初期の例は仮名書きであるが、後に『素的』の表記が広まり、昭和以降は次第に『素敵』が一般化したようである」。
今回のセリフを元々、四世南北が書いたのか、舞台公演の補綴(ほてつ)の方、あるいは演出関係の方が書かれたのかはわかりませんが、四世南北が生きた1755(宝暦5)年から1829(文政12)年の江戸時代には使われていたのは、おそらく間違いなさそうです。シネマ歌舞伎を通じて、当時の文化に触れた気がしました。
言葉は時代とともに、その意味も使い方も変化します。「ことばコトバ」では、こうした言葉の楽しさを紹介していきます。
(「ことばコトバ」第54回 ラジオ関西アナウンサー・林 真一郎)