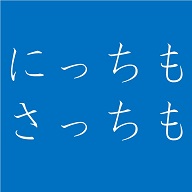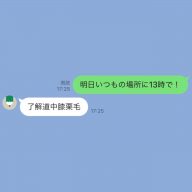先日、大相撲夏場所を観ていた時、「蒙御免(ごめんこうむる)」という言葉が目に留まりました。そういえば……と思い出したのが、今年の3月に春場所が行われた大阪の会場正面入口。そこにも、この言葉が書かれた木札が設置されていました。

調べてみると、この言葉は「相手の人、周囲の人々の許しを得る」(広辞苑第七版・岩波書店)というものです。以前、日本相撲協会のツイッターには、「(御免蒙とは)興行の許可を得たという意味で、御免札の屋根(上部)は大入りを願って入の字になっています。これも昔から続く伝統です」というような投稿がありました。
そう、かつて相撲興行は、「許可制」でした。江戸時代は幕府の許可=免状・免許がないと開催ができなかったのです。ですから、今でも会場入口の木札や力士の番付表などには「許可を得て相撲を開催しています」という意味の「御免蒙」と書かれています。これはその当時の名残で、今でも相撲の本場所が行われる会場にはこの木札があります。
そこで気になったのが、「御免」=「許可」という言葉。今は謝罪の意味で使われることが多いですが、そもそもどんな意味があるのでしょうか。
前出の広辞苑には…
「(1)免許の尊敬語。おかみのおゆるし(以下略)(2)免官・免職の尊敬語 ~(以下略)~(3)容赦・赦免の尊敬語。転じて、謝罪・訪問・辞去などの時の挨拶。(4)希望しないこと。いやなこと。(以下略)」とあります。そして他の例として「御免なさい」の項目に「(1)あやまち・非礼をわびる言葉」などとありました。
『新明解国語辞典 第八版』(三省堂)には、「ごめん」の最後に「ごめんなさい」の項目があり、そこには「謝罪の気持を表わす時の挨拶の言葉。〔親しい間柄では「ごめん」とも言う。〕」との記述。
このほか新明解には「省略的表現」という記載もあります。こうしたことから考えると、本来は「御免ください」のような表現だったのが、「御免なさい」「御免(ごめん)」などの短い表現になっていったと思われます。そして意味も、元々は「許可」だったものが、「許す」「許して」「許して下さい」のように転化、「謝罪」の言葉に変化していったと考えられます。
この連載にも何回か書いていますが、時代とともに言葉が簡略化されているものが本当に多いと感じます。とすれば、現代の「若者言葉」は、時代を先取りしているのでは…あるいは、何十年先には当たり前の表現として使われているのでは…そんなことを考える今日この頃です。
言葉は時代とともに、その意味も使い方も変化します。「ことばコトバ」では、こうした言葉の楽しさを紹介していきます。
(「ことばコトバ」第56回 ラジオ関西アナウンサー・林 真一郎)