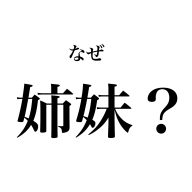物事のおもしろさをひきたたせる際に使用する「醍醐味(だいごみ)」という言葉。一般的に使われている言葉だが、じつは、意外なところから誕生したといわれている。
関西を中心に活躍するフリーアナウンサー・清水健と、落語家・桂米舞(かつら・まいまい)がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、醍醐味の由来などについて解説した。

醍醐味の由来は、奈良〜平安時代にあたる700年ごろの日本で作られていた乳製品「蘇(そ)」にあるといわれている。蘇は現在のチーズのような食品で、牛乳を加工した珍味として上流階級の間で広まった。
その後、蘇をさらに煮詰めて精製したヨーグルトのような乳製品「醍醐」が誕生。食べた人が口々に「最高の美味」と評したことから、優れた味のことを「醍醐味」と言うようになり、現在の形へ変化したといわれている。
由来にまつわる話を聞いた米舞は、「(醍醐は)よほどおいしかったんでしょうね」と当時を思い浮かべながらコメントを残した。
最高の美味を指す言葉として浸透していた「醍醐」だが、じつは、仏教の教えのなかでも“最高のもの”を意味するのだという。これを聞いた清水は「勉強になったなあ」と感心する様子をみせた。

醍醐味の由来について学んだパーソナリティーの2人は、“仕事の醍醐味”について「『声を聞いてホッとしました』と言われること」(清水)、「お客さんに笑ってもらえること」(米舞)と話した。
※ラジオ関西『Clip木曜日』より