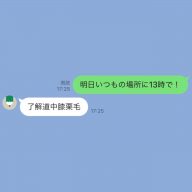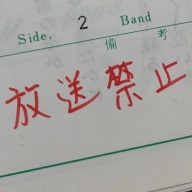「モールス信号でSOSを最初に使った海難事故です。船が沈むまで2時間半の時間がありました。通信士は最初のうち、これまでの緊急信号であるCQDを発信していました。その後、新たに国際信号として取り決められたSOSに切り替え発信したと聞いています。この事故がきっかけでSOSは広く浸透したといえます」と南さんは話します。

気になるSOSの意味については、「何かの略語でもないし、言葉としての意味もありません。SOSは『受信時の聞き取りやすさ』『発信時の間違えにくさ』などといった部分に意味があるのです」との回答でした。
そんなモールス信号は、現在でも使用されているのでしょうか?
「30年前、私が学生だった頃は電信技術として必要とされていたため大学の授業で教わっていました。モールス信号を光で表したものを『発光信号』といいますが、こちらも学内で試験がありました」と南さん。
しかしその後「衛星通信が発達したことで1999年2月に国際海事機関(IMO)の取り決めにより、全般的に船舶の通信は衛星通信に完全に移行。モールス信号は縮小していき、非常用の通信手段としてもあまり使用されなくなりました。そのため船舶の世界では、モールス信号や発光信号を航海士が知っておく必要がなくなったのです」(南さん)
技術の進歩と共に、使用される機会が減ったモールス信号。ただ、完全に使われなくなったわけではなく、自衛隊などでは現在も使用されているそう。というのも、モールス信号は国際的に共通した信号のため、海上において米軍とのやり取りで使われることもあるといいます。
ちなみに、商船で働く航海士も知識のひとつとしてモールス信号を覚えてはいるようですが、実際に使うことはほぼ無いのだとか。
「緊急事態に陥ったときは、ボタンを押せば衛星回線を通じて近隣の船舶や陸上に緊急信号が一斉に送信されます。緊急信号を送る措置ができない場合でも、救命艇には衛星を使って信号を出す機械(イパーブ)が積まれているので、位置を知らせることができます」と南さんは説明しました。

☆☆☆☆
現在も、一部のアマチュア無線家の間などでも使われているモールス信号。他の信号の由来も調べてみると興味深い発見があるかもしれません。
(取材・文=迫田ヒロミ)
※ラジオ関西『Clip』2025年2月11日放送回より