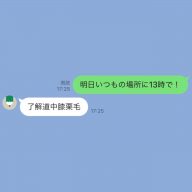ナイフやフォーク、スプーンなど、食卓を彩る「カトラリー」。もともと西洋で使われていたものですが、新潟県燕市で日本人のためのカトラリーがはじめて作られるようになりました。
その後、いちごをつぶすためだけに作られた「イチゴスプーン」が大ヒット。一時期は燕市が手がける定番商品となりました。
なぜイチゴスプーンがヒットしたのか、そもそも燕市はどのような町なのか? カトラリー製造の開始から今年で108年を迎える小林工業株式会社の小林さんに、同市の歴史やイチゴスプーンについて話を聞きました。

――イチゴスプーンを開発したきっかけは?
【小林さん】 イチゴスプーンは1960(昭和35)年に誕生しました。当時、日本では小さくてすっぱい輸入のいちごが多かったんです。日本産のいちごも同時期に誕生したのですが、まだまだ甘くなかった。そのため、いちごは「練乳がけ」か、つぶした後に砂糖と牛乳をかける「イチゴミルク」にして食べることが主流でした。そこで、つぶしたいちごをそのまま食べられるスプーンを製造できないかと思い、燕市の金型彫金職人・青山彫金師にお願いして開発に至りました。
最初の試作品は無地のスプーンで底が平らになっているだけだったので、いちごがつるつるすべってお皿から飛び出したりして思うようにつぶせず……。当時の工場長が「すべり止めに何か模様を入れてくれないか」と青山さんに依頼したところ、「いちごのタネの模様はどうだろう」と発案いただきました。
模様入りも何度も試作を行ったのですが、なかなか難航し……。青山さんが改めて観察し、実際のいちごのタネ通りに配置してみたところしっかりホールドされるようになりました。そうして、いちごのタネ模様が彫られた“すべらない”イチゴスプーンが誕生しました。
――商品化にかかった期間は?
【小林さん】 商品化するまでに3年かかりましたね。はじめはステンレスのなかでも柔らかい素材を使っていたのですが、急に固まってしまうという特徴からなかなか言うことを聞いてくれず……。習得するのに2年かかりました。
――なぜ燕市は“金属洋食器の町”として有名になったのでしょうか?
【小林さん】 もともと燕市は水害多発地域だったので、手に職をつけるのが難しい地域でした。そのため、幅広く産業に取り組んでおり、農機具、釜、アイロン、火箸、灰ならし、キセルなど、生活用品にまつわる商品を数多く製造していました。そして、その幅広く取り組める姿勢がカトラリーの製造場として最適だったのです。
スプーンやナイフ、フォークのすべてを1本1本手作りで作れるのはここ、燕市だけでした。戦後にはステンレスカトラリーの量産に世界で初めて成功し、生活用品を幅広く扱ってきたこれまでが報われる結果となったのです。その後、アメリカを中心に世界からのオファーが殺到し、急成長を遂げました。
また、昭和35年は東京タワーができた年でもありました。さらに、カレーがご家庭の食卓に登場するなど、洋食文化が身近に感じられるようもなりました。カトラリーもその変化の波に乗り、日本人向け商品の需要が高まってきました。