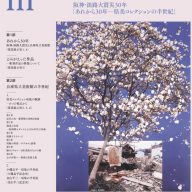平安時代末期から今田町立杭を中心に生産され続けている丹波焼をはじめとし、兵庫県丹波篠山市ではやきものが盛んに作られてきた。今回の「リモート・ミュージアム・トーク」は、同地に集う作家たちの多彩な名品を集めた、兵庫陶芸美術館の特別展「TAMBA NOW+ 2025 ―変わらぬ風景、進化するやきもの―」。同館学芸員の高村恵利さんに作品の見どころなどを解説してもらう。
☆☆☆☆☆
兵庫陶芸美術館では、2月28日(金)まで、特別展「TAMBA NOW+ 2025 ―変わらぬ風景、進化するやきもの―」を開催しています。
当館では、開館10周年を迎えた2015年より、5年を節目として、丹波篠山市域で活躍している作家を紹介する「TAMBA NOW+」を開催してきました。本展はその第3弾として、総勢94人の近作を集めました。丹波で生まれた多様なやきものの「今」をご披露します。


まずは、柴田雅章《飴釉掛分スリップウェア大鉢》です。
スリップウェアとは、化粧土(スリップ)を用いて装飾したうつわ(ウェア)のことです。本作は、板状の素地に、白と黒の化粧土を掛け分け、さらにその上に動きのある曲線が描かれています。その後、型を用いて鉢形に成形し、見込み全体に飴釉が掛けられています。柴田氏は、その材料や制作方法にも重きを置き、作品には丹波の土を用いて、薪の窯で焼成しています。

市野雅彦《untitled》は、3本の円筒が絡み合い、曲がっています。その様子はまるで鉄のようにも見えます。
一方で、制作過程には、釉薬をかけずに焼成する、焼き締め技法を用いることにより、近づいてみると、作品の表面にはざらっとした土の荒い質感があらわれています。色味が抑えられた本作は、加飾しないことによって、形の美しさが際立ち、見るものを魅了します。

最後は市野秀作《灰紬彩壺》。丸く整えられた器体の全面に、鮮やかな釉薬がたっぷりと流れ、緑・青・ピンクのグラデーションが美しい景色を作り上げています。本作に用いられている3種の釉薬は、灰釉に、コバルト(青)、鉄分(緑・ピンク)などを加えて調合した、市野氏独自のものです。ロクロ成形後に削り入れたラインは釉薬の流れを変化させ、360度異なる表情が楽しめます。