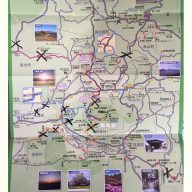最大震度7の揺れを2016年4月14日夜と16日未明に2回観測した熊本地震。その「本震」から5年を迎えた。
あのとき、被災者の一時避難所として、また復旧活動に向かう自衛隊や警察、工事車両の中継基地として大きな役割を果たしたのが、被災地の「道の駅」だ。いま、国も「道の駅」を防災拠点として位置付ける取り組みに力を入れている。4月22日の「道の駅の日」(一般社団法人全国道の駅連絡会制定)を前に、道の駅「阿蘇」(熊本県阿蘇市)の下城卓也駅長に、大規模災害時に道の駅が果たす役割と課題を聞いた。今回はその【後編】。
熊本地震で各地の道の駅が果たした防災拠点としての役割の多様さには驚かされるが、そうした活動の裏で直面したのが、復旧支援に奔走するスタッフを支える体制の脆弱さだった。
「あのとき特に困ったのは、道の駅のスタッフたちも被災者だということと、公務員ではなく民間人だということ。自分たちも避難所にいれば支援物資や炊き出しが支給されるのに、そこに道の駅の食料をもっていくけど自分たちは食べられない。地域のためにも復旧復興支援に役立ちたいが、どこまでやるべきか。そんなジレンマがたくさんありました」(下城氏)

道の駅ときくと公的施設の印象があるが、それは実態と大きく異なっていると下城氏は指摘する。
「道の駅の多くは、建物を建てたのは行政だが、運営は民間。働くスタッフは民間人だ。道の駅を防災拠点として活用するなら、貯水槽や非常用電源といったハード面だけではなく、ソフト面の支援が必要。道の駅と自治体が防災協定を結ぶなど、スタッフが安心して復旧支援に取り組める体制を整えていくべきだ」(下城氏)
熊本では昨年2020年7月、豪雨水害が襲い県南地域を中心に甚大な被害出たことは記憶に新しい。下城氏ら熊本の道の駅では、被災エリアを支援するため、地元企業と新商品「しあわせふりかけ」を開発した。
「ふりかけを日本で最初に作った熊本のフタバ社との共同開発。ふりかけなら全国の道の駅でも販売してもらいやすい。九州を中心に全国の道の駅で扱ってもらっており、売り上げの一部を被災地の復興に充てている」