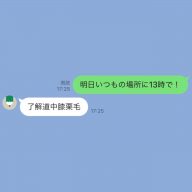では、「天然」と「養殖」は誰がいつから言い始めたのでしょうか?
「たいやき ともえ庵」(東京都杉並区、以下、ともえ庵)によると、「天然モノ」はかなり新しい表現であり、2002年に発刊された本『たい焼の魚拓』の中で、著者の宮嶋康彦さんが、たい焼きを分類するのに使ったのが最初だと言われているそうです。
写真家の宮島さん。たい焼きが大好きで、当時は“絶滅”寸前だったという「天然モノ」のたい焼きを求めて日本各地を巡り、たい焼きの魚拓を集めた『たい焼きの魚拓』を出版しました。ともえ庵の「全国一丁焼きのたい焼き店調査」によると、現在は一丁焼きのたい焼きを提供するチェーン店が増えたことで、天然モノのたい焼き店は増えてきている、とのことです。
ちなみに、たい焼き自体はどのように誕生したのでしょうか? ともえ庵によると、諸説あるそうですが、江戸時代に発祥したらしい「文字焼(もんじやき)」にルーツを持つとのこと。
「文字焼」とは、熱した鉄板または銅版の上に、小麦粉に砂糖を混ぜて水で溶いたものを流して文字や絵の形に焼いたもので、鯛や亀、宝物など縁起の良い形が人気だったとされています。その文字焼きに、やがて餡を入れるようになりました。そして、鯛の金型ができるなど高度に発展し、現在のたい焼きにつながっていったのだそうです。
天然にも養殖にもそれぞれの良さがある「たい焼き」。購入される際はどちらのたい焼きなのか、気にしてみてください。
(取材・文=宮田智也 / 放送作家)