最近の日本人は怒らなくなったと言われます。また反抗期がない子どもたちも年々増えているそう……。しかし、ロック、ブルース、ヒップホップ、演歌など音楽の多くは、そもそも社会への不満を歌った反抗歌、プロテストソングとして発展しました。怒りを忘れた日本の音楽シーンに未来はあるのか……。中将タカノリ(シンガーソングライター・音楽評論家)と橋本菜津美(シンガーソングライター・インフルエンサー)が昭和の”怒りの曲”を振り返って語り合いました。
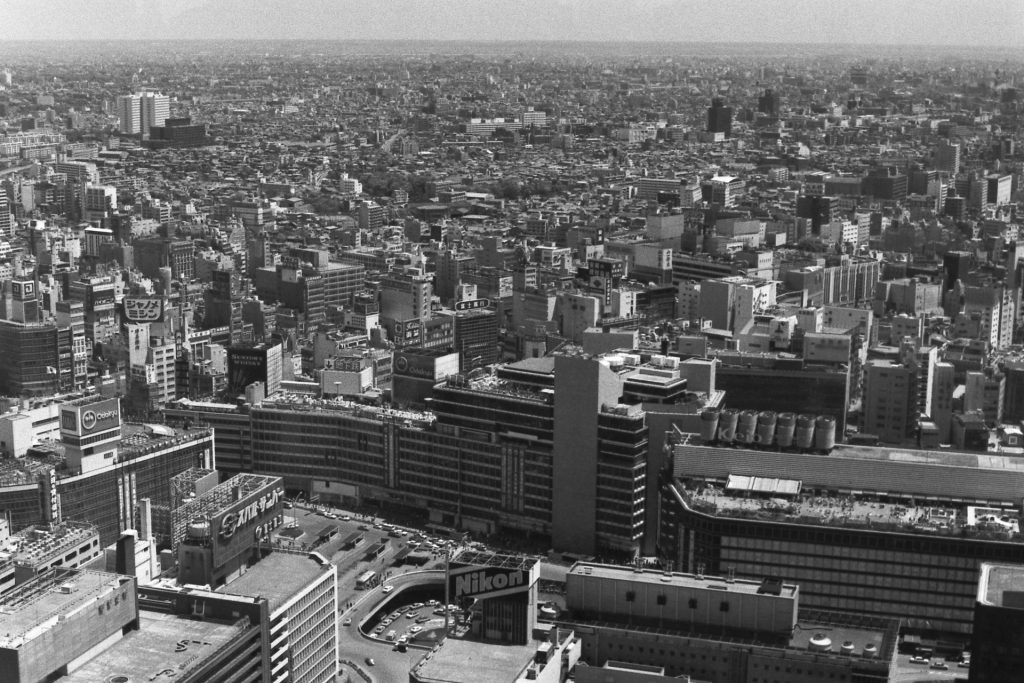
※ラジオ関西『中将タカノリ・橋本菜津美の昭和卍パラダイス』2025年4月4日放送回より
【中将タカノリ(以下「中将」)】 最近、若者があまり怒らないって言うじゃないですか。反抗期がない子も増えてるそうだし。
【橋本菜津美(以下「橋本」)】 えっ! そうなんですか? 私が学生の頃は「反抗期がないのは発達に良くない」って言われてました。
【中将】 親子関係が友だちみたいな感じのまま大きくなっちゃうんだって。それに社会への怒りや不満をあからさまにするような人も減ってるよね。
【橋本】 そうですね……「世の中を良くするために選挙に行こう」という流れはあるけど、日頃から社会や政治を意識している人は少ないだろうなと思います。私を含めてですが。
【中将】 今なんて税金はどんどん上がるし、ポシャったけど高額療養費負担の上限額を引き上げるみたいな話もあったじゃないですか。もし目の前で財布からお金を抜かれたらみんな怒るだろうけど、税金とかでシステム的にお金を取られることにはそこまで怒らない。もうちょっと政治に対する怒りの感情はあったほうがいいと思うんだけどね。
そういうわけで、今回は昭和の怒りの歌、反抗歌をひも解きつつ、怒りの必要性を見つめ直したいと思います。2020年にヒットしたAdoの『うっせえわ』も近年珍しい怒りの歌でしたが、昭和にはもっと数多くの怒りの歌が存在しました。1曲目に紹介するのはフォークの神様・岡林信康さんで『くそくらえ節』(1969)。
【橋本】 いいねぇ、気持ちいいくらいに怒ってるわ(笑)。
【中将】 当時は安保闘争、学生運動など社会、政治の怒りが暴力的に噴出していました。この曲は歌詞からも資本家、政治家への怒りを歌ったものとされることが多いですが、そもそもは岡林さんが交流のあった養護学級の子どもたちが画一的な学校教育の中でお荷物扱いされ、健常な生徒からもバカにされるのを目の当たりにした怒りから生まれたそうです。
【橋本】 怒りの曲なんだけど、楽しく聴けるように仕上がっているのがいいですね。でも最近だと学校の先生や会社の上司が厳しく叱ったり暴力を振るうことはNGとされているし、こういった直接的な怒りがわきにくくなってるのかなとも思いました。
【中将】 そうですね。もちろん暴力は良くないんだけど、あまりにがんじがらめで効果的な指導ができなくなってきてるという話もありますよね。
さて、次に紹介するのは同じくフォークの名曲、吉田拓郎さんで『イメージの詩』(1970)。








