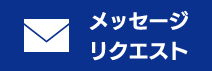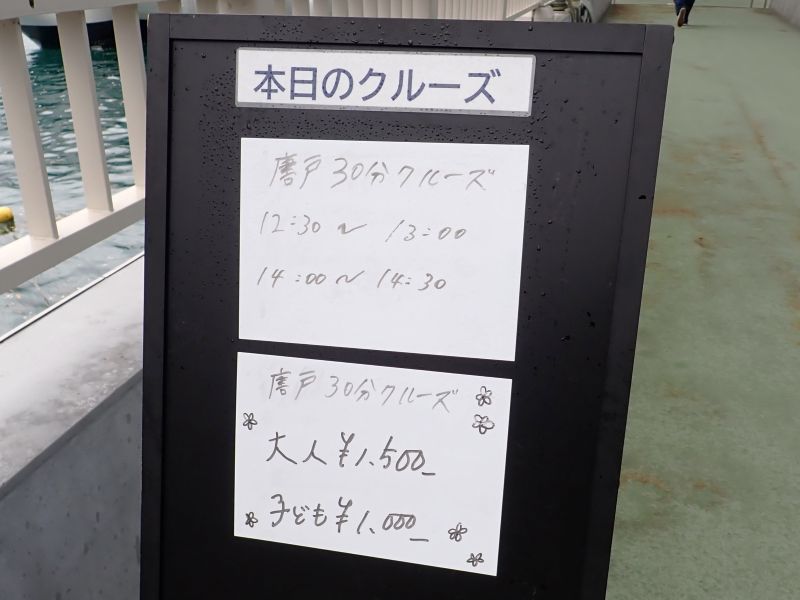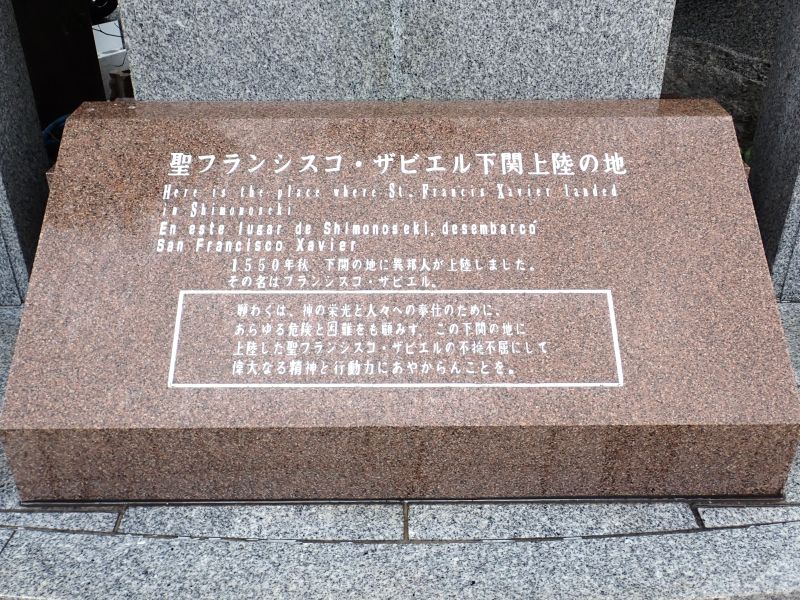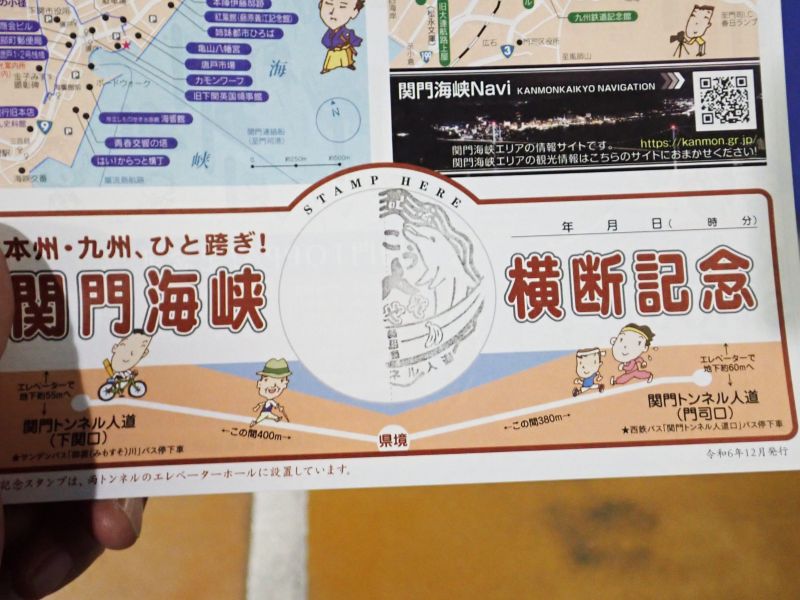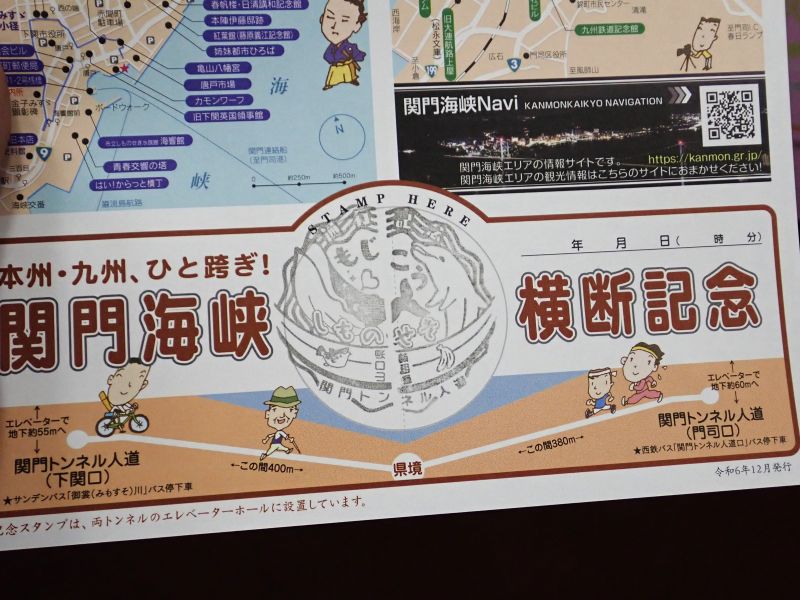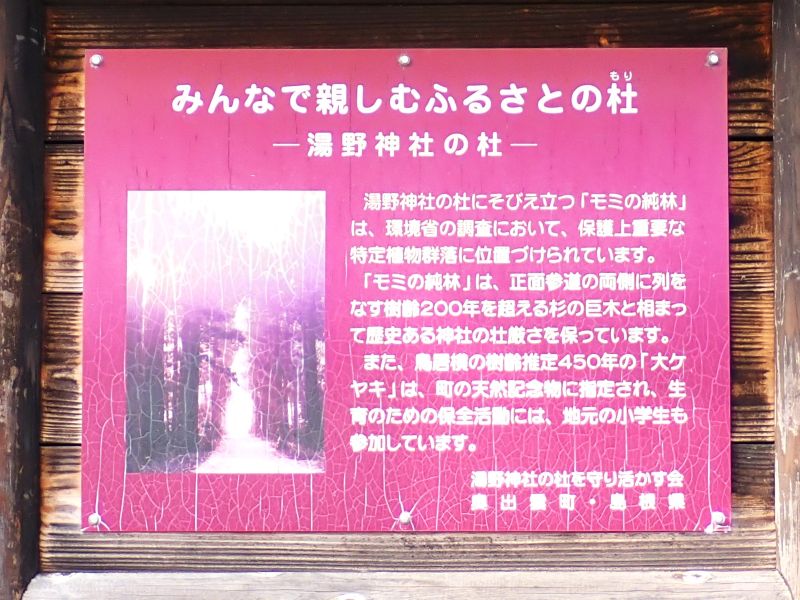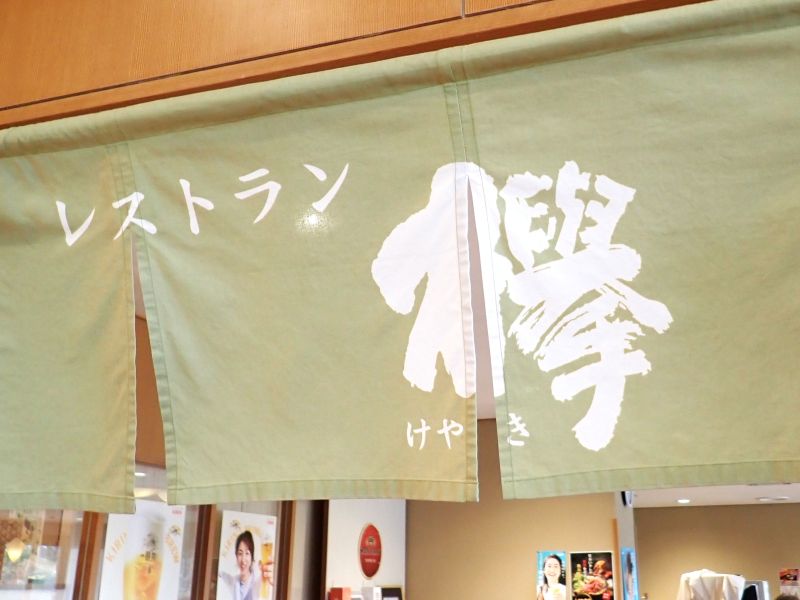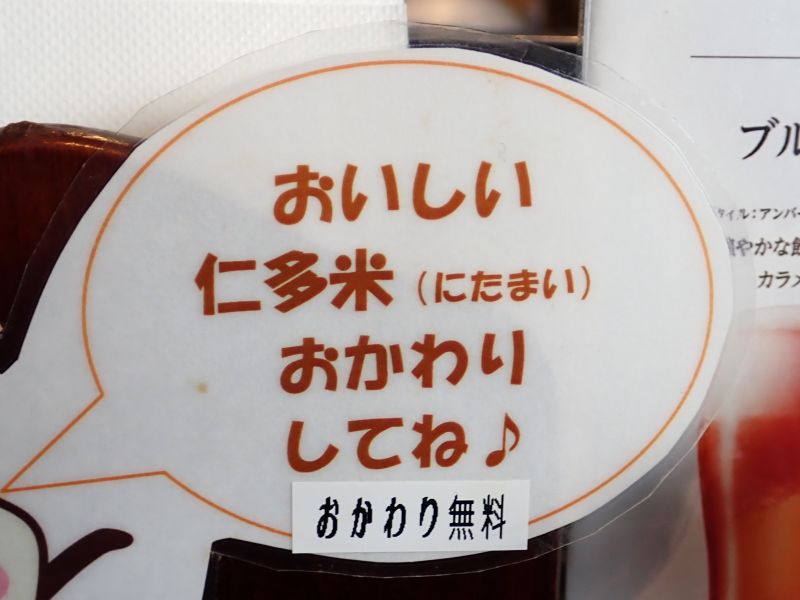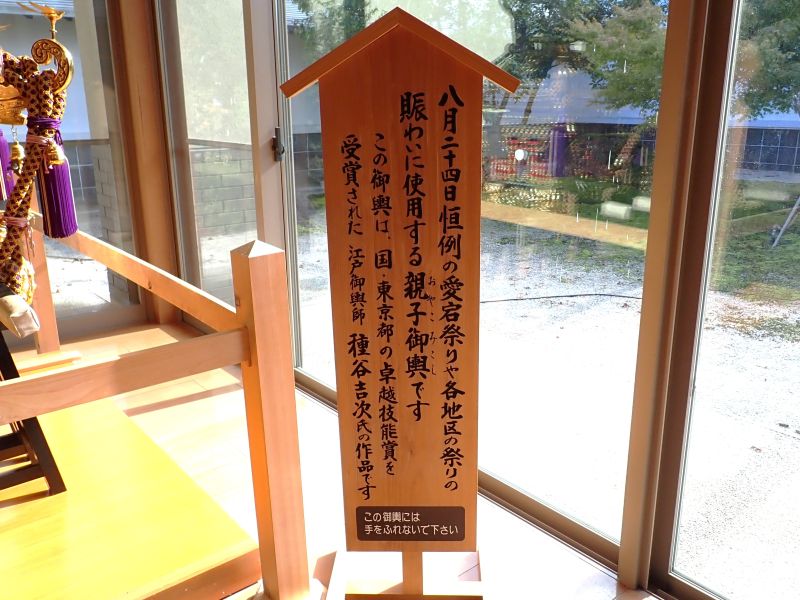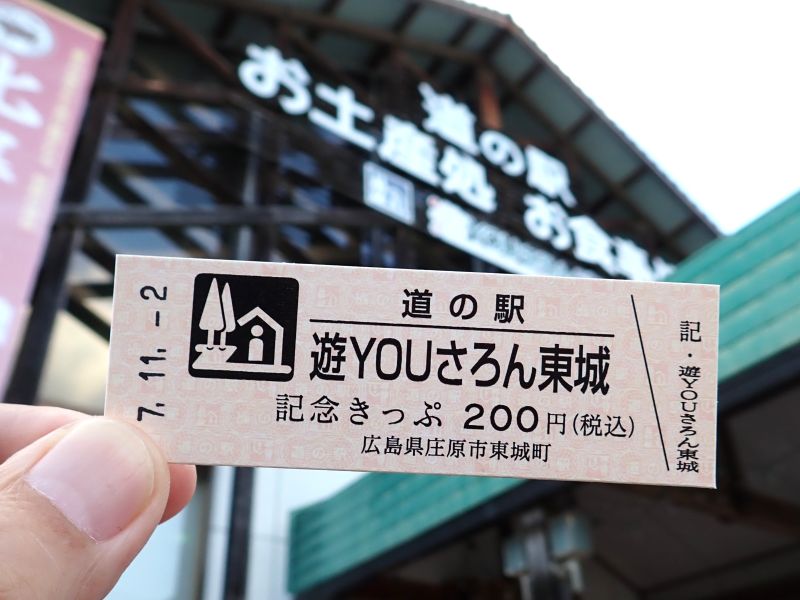2026年になりました!
どんな新年をお迎えでしょうか。
本年も引き続き「朝は恋人」を宜しくお願いします!
さて龍野散策の続き・・・
城見学のあとも城下町をブラブラ
童謡「赤とんぼ」の作詞者である三木露風の生家

神戸地方裁判所龍野支部の建物

白壁に沿って石を敷いた水路がありました

ハート型の石を発見!

たつの市認定の龍野こども園

醤油の郷・大正ロマン館。元々は龍野醤油同業組合(現:龍野醤油協同組合)が大正13年に建設した旧組合事務所で、大正ロマンを感じさせるモダンな洋館です。

地産地消カフェや地場産品ショップなどもありました

「たつのにんにく万能だれ」を買ったのは「だれ」?それは私(笑)炒め物などに使ってみましたが美味しいです

旧カネヰ醤油工場群の建物。現在は不定期で「ゐの劇場」として不定期にイベントが開かれているそうです
水路で魚が泳いでいました

路地散策

播磨の小京都といわれる由縁の町並み

市の龍野伝統的建造物保存地区は国の重要伝統的建造物群保存地区に設定されています

龍野圓光寺(たつの・えんこうじ)

宮本武蔵修練の地の石碑がありました

剣豪宮本武蔵ゆかりのお寺です

梅玉旅館

渥美清主演の「男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け」で寅さんが泊まった旅館

寅さんの映画ロケ地で宴席で寅さんがぼたんと出会う旅館です

「矢野勘記念館」龍野の文化人の足跡をたどる資料館で、三木露風をはじめ、哲学者の三木清、反戦・田園詩人の内海信之、一高寮歌「嗚呼玉杯に花うけて」作詞者の矢野勘治ら4人に関する文献や資料を一堂に集め展示されている施設です

街の中心部へ

和レトロモダンな姫路信用金庫の建物

側溝の蓋にトンボが!

マンホールもトンボ

カラフルなキャラクターデザインの蓋

こんな蓋もありました
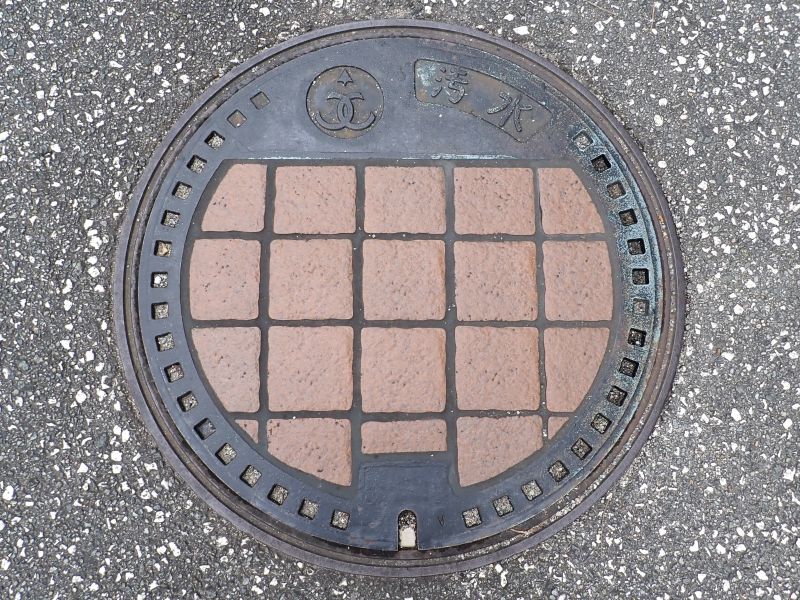
ブラブラ歩いているだけで楽しい町並み散策でした
播磨の小京都・龍野散策つづく・・・