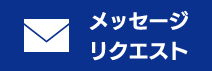お弁当の淡路屋のJR貨物コンテナ弁当シリーズの新作第3弾がきょう1月6日(土)に発売になりました。

水色の18D型がモチーフ

第1弾「神戸のすきやき編」、第2弾「明石の鯛めし編」に続く第3弾は「京の鶏めし編」

京都をイメージした内容で、鶏照焼、鶏つくね、味付け油揚げ、味付けわらび、姫竹、葱煮、人参煮、すぐき漬けが入っています。
祇園原了郭の「黒七味」付き!

空き箱は小物入れなどに使えますが、溜まってくると台車が欲しくなりますね。

我が家のNゲージ鉄道模型の18D型コンテナ

またひとつコレクションが増えました(笑)

価格は1つ1,680円(税込)
※お店での予約・取り置きも可能です。
番組内容
懐かしの名曲を中心に三上公也アナウンサーのセレクトで、月曜日から木曜日の朝のひとときを音楽で彩ります。
また、エンタメ、スポーツ、ライフスタイルなど、一日の始まりに入れておきたい情報もお伝えします。
-
-
正月三が日もあっという間に過ぎて今年最初の週末を迎えようとしています。
元日に起きた能登半島地震では犠牲になった人の数が日々増えています。多くの行方不明者の捜索も行われていますが、生存率が大幅に下がるとされる発生から72時間が経過しました。余震も起きる中での捜索は二次災害の危険も伴うことから思うように進まないとも聞きます。明後日以降は冬型の気圧配置が強まってくるようですが、なんとか無事でいて欲しいと祈るばかりです。さて来週の特集コーナーは・・・
1月 8日(月・祝)
8時台の洋楽特集、9時台の邦楽特集とも「勝負事の日」によせて
「ゲーム」と名の付くタイトルソング集1月 9日(火)
8時台の洋楽特集、9時台の邦楽特集とも「語呂」から
「行く・GO」タイトルソング集1月10日(水)
8時台の洋楽特集は「いい王の日」によせて
「キング・王」ソング集
9時台はゲストに兵庫県福崎町長の尾﨑晴さん
を迎えてお送りします。1月11日(木)
8時台の洋楽特集は
「棚番111」ソング集
※1965年4月頃に登録された男性ボーカルものが収納されています。
9時台は月に一度の「こちら知事室!」
兵庫県知事の斎藤元彦さんを迎えてお送りします。※なお1月11日は「朝は恋人放送1000回」となります。
リスナープレゼントも用意していますのでお楽しみに!リクエストやメッセージをお待ちしています。
番組メールアドレスは↓
asa@jocr.jp※予告なく放送内容を変更する場合があります。ご了承ください。
夜にはライトアップされる神戸駅前のD51蒸気機関車

夜は逞しさを感じます。 -
あけましておめでとうございます!

神戸駅前のD51(デゴイチ)は迎春バージョンに!

朝は恋人は今日1月1日も生放送。本年も引き続き宜しくお願い致します。 -
「今年1年を振り返る」ー今年見かけたヘッドマーク付き車両。まずは引退関連から。JR和田岬線を走っていた103系車両。

今年3月で運行を終了した国鉄時代の車両です。

引退はしましたが先日網干総合車両所明石支所で姿を見かけました。9月には見学会も行われたようです。

「幕を下ろす」といえば能勢の妙見の森。ケーブルカーをはじめ森施設すべてが今月3日で営業を終えました。

それに伴い能勢電鉄で「ありがとう」「さよなら」のヘッドマーク付き車両が運行されました。

北神急行車両の7000系が今年8月に引退し、9月に神戸市北区の谷上車庫でさよならイベントが開催されました。

「周年」では山陽電車が明石・姫路間開業100周年を記念してヘッドマークを掲出

前後2か所ずつで計4種類のヘッドマーク

中には1つだけの車両もありました。来年3月中頃まで掲出運行予定とのこと。

その色合いから「ウルトラマン車両」と呼ばれる神戸電鉄3000系。デビュー50周年を迎えてデビュー当時の復刻カラー車両がお目見え。

50周年といえば神戸市北区の区政50周年を記念したヘッドマーク付き車両も3000系車両に掲出されています。

阪急電鉄では「大阪梅田新駅開業50周年」を記念したヘッドマーク付き車両も登場。

阪急電鉄といえば春は「さくら」、夏は「天神祭」「祇園祭」、秋は「もみじ」などその季節に応じていろいろなヘッドマークが掲出されていますが、コラボラッピング車両もいろいろ。

現在走っているのがイラストレーターのナガノさんの発信する漫画「ちいかわ」コラボ車両。来年3月28日(木)まで運行中。

そしてクリスマスには「阪急クリスマストレイン」も登場

阪急大阪梅田駅に留め置いた車両内でクリスマスイベントが開かれていました。列車内に装飾を施しサンタさんもいましたよ。

そして今年の関西話題のトップは「アレ」ですね。

プロ野球阪神タイガース日本一を祝し感謝のラッピングトレインが走っています。

阪神8000系車両にはヘッドマーク掲出フックなどがないためステッカー対応。運転席には副標を掲出

5000系車両には掲出場所があり、オリックスとの「なんば線対決」の際にこんなヘッドマークが掲げられました。

5000系ジェットカーも車両数が少なくなりました。2024年度中には最新の5700系に置き換わる予定だとか。

今年も番組ブログをご覧いただきありがとうございました。来年も引き続き宜しくお願いします。
そして良い年をお迎えください。

-
原鉄道模型博物館からほど近い場所にもうひとつの鉄道ミュージアムがあります。

それが京急グループ本社ビル1階にある「京急ミュージアム」。来年1月に開館4周年を迎える施設です。

現在入館は1日3回の入れ替え制で、1回目と2回目はWEBによる事前予約が必要とのこと。

屋外展示の「ケイキューブ」

この日はあいにく時間が合わず入館が叶いませんでしたが、外からデハ236形が見えました。

入館無料とのこと。次回予約して訪れてみることにします。
京急ミュージアム公式サイトはこちら