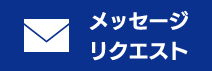夏場になると、陽ざしの強い日が多くなりますが、こういう時に運転していると、トンネルから出た瞬間や、薄暗い地下駐車場から地上へ出る時に「まぶしい!」という体験をした方も多いのではないでしょうか?
特に白い車や荷台が銀色のトラックが前を走っていると、突然「前の車が消えた」ように感じることがあります。 なぜ、このような現象が起こるのでしょうか?
例えば白や銀色などの明るい色の車が強い太陽光に照らされると、全体が光に包まれたように見えて、車が見えにくくなります。 これを「蒸発現象」といいます。
その逆で、空はまだ明るいのに路面近くが薄暗い夕暮れ時や、日中に照明のないトンネルに入った直後などは、色の濃い車が周囲の暗さと同化してしまうことがあります。
これを「溶け込み現象」といいます。
これらの現象が起こりやすい条件下では、自分だけではなく、他の車のドライバーも同じような感覚になると考えてください。
もしも自分の車が、思い切り明るい色または暗い色をしているなら、後方からの追突されないように、
・昼間はトンネルを出た直後、テールランプを少し長く点灯させておく。
・夕暮れ時は早めにテールランプを点灯させる。
といった対策が大事です。
また、トンネルの出口付近で起こる「逆光現象」も危険です。
夕暮れ時には太陽光が、正面からトンネルの出口付近に差し込むことがあります。
この時、前の車が光に包まれて見づらくなって、後続車のドライバーがとっさにブレーキを踏んでしまいがちです。
ですから、トンネルの走行する時は、時間帯や周囲の状況、車間距離などに注意を払い、安全に走行することが肝心です。

ご予約・お問い合わせは 0120-50-1515