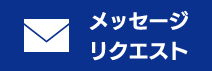車の運転中に災害に遭遇した時、どう対応すればいいか、皆さんご存知ですか?
まずは、運転中に地震が起きた時の対処法です。
①ハザードランプを点滅させ、周囲の車や歩行者の状況を確認しながら、路肩へ車を寄せて停止させます。
あわてて急ブレーキをかけたりすると、後ろから追突される恐れがあるので、ゆっくりと減速して止まりましょう。
②地震がおさまるまでは、あわてて車の外へ飛び出さずに車内で待機して、携帯電話やラジオなどで地震情報や各地の被害状況などを確認してください。
③万が一、トンネル内や橋の上で地震が発生したときは、出口が見通せる位置にいるなら、ゆっくり走行しながらトンネルを抜けましょう。
次に、津波に遭遇した場合です。
①津波警報が発令していたり、周囲の道路が損傷や渋滞で走行できない時は、車を置いて避難します。
この時、エンジンを切って窓を閉め、車のキーはつけたままで、ドアをロックせずに離れましょう。
キーをつけておけば、車が緊急車両の通行の妨げになった際に救急隊員が移動させることができます。
②近くに避難するような場所がなく、やむを得ず車で移動する場合は、信号や街灯が停電で動いていないこともあるので、周辺の道路状況に注意して慎重に運転してください。
最後に、ゲリラ豪雨に遭遇した場合です。
①アンダーパスを避けて移動しましょう。
アンダーパスは、周辺よりも掘り下げた状態の道ですから、豪雨の程度によっては、数メートルもの深さに水がたまる恐れがあります。
絶対にアンダーパスは避けて移動してください。
②「行けるかも」という過信は禁物です。
アンダーパス以外でも、周辺の河川や下水道などの状況次第で、普通の道路が冠水することもあります。
「このくらいなら」と思って進んでいたら、いつの間にか車が半分沈んでいたということもあります。
少しでも冠水している道を通るのは避けてください。